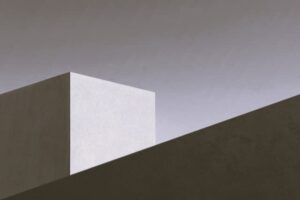講義をおこなうにあたり資料を作っています。
内容は『養生訓』を用いての産前産後の健康法について。
はじめに作者である貝原益軒についてパワーポイントを作成していました。
貝原益軒は儒学者なのですが、その始祖は中国の思想家・孔子。
「儒」は「柔和で礼を重んじる人」の意味があり、人としての道(仁・礼・義)、社会秩序を保つための学問。
この考えは、日本や朝鮮、ベトナムにも伝わって、政治・教育・道徳に大きな影響を与えました。
養生というと何となく守ることが多そうなのは秩序と道徳があるから。
しかし、それを無理に統制してしまえば害になる。
私が「〇〇しないと駄目」ということを言わないのは老子による影響が大きいのですが、人間は理性がありますから力を抜いて、自然に従って身を任せれば良い。
けれど儒教の教えがあるから「〇〇でなければならない」という考えで物事を考えてしまうわけです。
日本では「努力して学び、礼儀を守り、社会のために尽くしなさい」という考えがありますよね。
けれど、それにこだわってしまうと苦しくなってしまいます。
だから、そうしなければ良いというわけではなく、陰陽の考えを用いればどちらの考えもバランスよく使うということが大切だと思います。
ただ、「自由だ!」というのは実際には不自由であって「不自由だ・・・」と思っている時は実際には自由なわけです。
例えば「お金がない」と思っていても必要のないものは買っていたり、「時間がない」と言っていても平等に時間は流れるわけです。
どの視点でどのように考えるか。
それが大切なように思えます。
先日、娘が音楽の授業を休みたいがゆえに夜中まで起きて翌朝に寝坊していましたが、それは遅刻するから行きたくないという理由を作るために誤った自由を自分に与えてしまったことで、実際は居心地が悪さという不自由を手に入れてしまっていました。
この場合、学校に行かないことで自責の念が強くなってしまい、また自分に対して嘘をついていることが苦しみを生んでいるようでした。
ですから「〇〇でなければならない」とルールを重んじてしまうと、生きにくくなってしまいますから、自然体であることを自分に与えて欲しいいのです。
けれど勘違いしてしまう部分があって、基本としては人は道が必要であるということ。
仁も礼も義も知らないと社会生活を送るのは困難です。
「知らないといけない」ではなく知っていた方が良い。
それを表面的にやるがために苦しんでいる人が多く見受けられます。
だから、新興宗教や占いにハマってしまったり、サプリメントや漢方、酒やギャンブル、鍼灸や整体に依存してしまうのでしょう。
こういったことを知らないと、そういったストレスのはけ口を探し続け消耗してしまいますし、人に依存して他人を傷つけます。
さらには自分の心身を傷つけるようにもなります。
それはとても不健康ですよね。
ある人は変形性膝関節症で膝が痛いのですが、正座ができないことを悪いように思っています。
この時の基準は正座ができることがゴールです。
しかし、日常は椅子に座り、ソファーで過ごしています。
さて、正座をする必要はあるでしょうか?
私には日本人だから正座ができないといけないということに執着しているようにも思えます。
そのことよりも「余生を自分の足で生活する」ということの方が大切なのに、目の前のことに執着してしまうのは完璧でなければいけないというような思い込みによるのだと考えることが出来ます。
歳を重なれば膝の軟骨は摩耗しますし、筋肉も落ちてきますよね。
そうすると関節は「ポキポキ」と音が鳴るわけです。
みな、その音に執着をするがために、さらに音を鳴らして炎症を生むのですが、それにより「痛い」「治らない」と思い込みます。
みなさん、自分を傷つけて今あることを肯定する(確認する)必要などないのにそれを繰り返す。
そのことを人生の中でどのように気づくか。
みなさんの人生は自由ですから、日々心地よくあることを求めて欲しいです。
そんなことを資料づくりをしていて思いました。