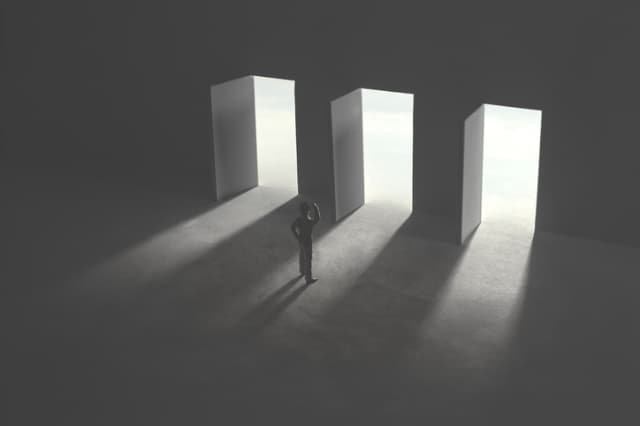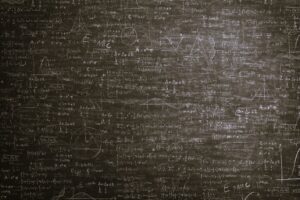これまでこのブログを幾つかUPしてきましたが、小難しい内容だと思う方もいるかもしれません。
ただ、SNSであがってくる鍼灸師の投稿をみていて思うことは、どれも同じ内容を上書きしているということ。
「このツボは〇〇に効きます!」と書いてありますが、正直なところ押しただけでは効きません。
ツボというものは性質があります。
触れる程度でよいもの、押して効果があるもの、鍼により効果があるもの、灸により効果があるもの。
そして深さ、刺激量の加減があります。
そしてツボには大小ありますから、押せば良いというものではないのです。
ですから私は引き続きこの形で発信を続けていきたいと思います。
さて、今回は【鍼灸は何をどうしているのか】ということについてですが、このような概要があります。
鍼灸は患者の病態の変動を観察することが根本です。
その中で得た情報から「虚」「実」に対して診断即治療をおこなうことが原則であり鍼灸の本道です。2000年以上も前から中国に伝えられた最古の古典「素問」にも、身体の調和が崩れると病気になると紹介されていますが、起きている現象(標)を和らげ、その現象のもとにある体調の異和(本)を整えることが鍼灸本来の目的です。このように身体全体のバランスを良くすることによって新しい病気は短期間で治すことは容易です。
しかし拗らせた症状は施術を長く続けなければ効かないものです。悪性のもの、古い病気でも比較的にすぐ良くなることはありますが、一般に鍼灸や漢方というものは5年間の病には5年をかけるという心構えで、鍼灸師もされる方も根気よくやっていかないと治らないものです。参考書籍 岡部素道「鍼灸治療の真髄 経絡治療五十年」|績文堂刊 1983
いかがでしょうか?
鍼灸師は必ず施術をおこなう中で「病態の変動を観察」します。
以前、行徳地区の漢方薬店に漢方を買いに行ったことがあるのですが、どのように処方しているのか質問をしたところ「感覚です」という答えが返ってきたことに残念な気持ちになったことがあります。
なぜなら、それは主観であって患者の病変の変動という客観性に乏しいからです。
このような鍼灸師が多いのも事実です。
だから私はその違いをもって施術をおこなっていることを発信しています。