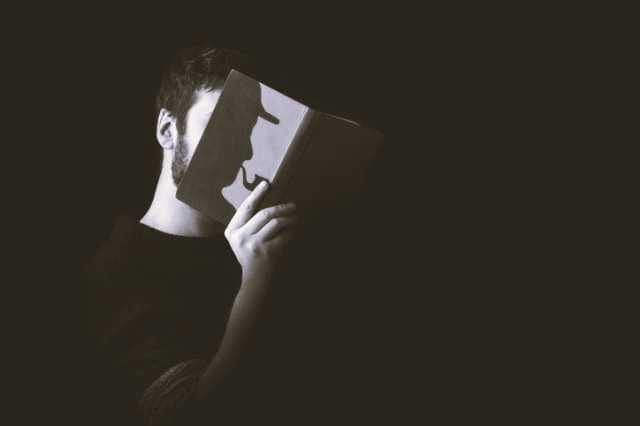今日は【鍼灸の概要(2)】として、外科医・鍼灸師・医学博士の間中喜雄先生の書籍か抜粋して記事を書いていきたいと思います。
鍼灸は中国伝来の古い理学療法です。
日本の医学は西洋医学一辺倒であるため鍼灸や漢方を民間療法として蔑視する傾向にあります。
しかし、実際には東洋医学における鍼灸の施術対象は、西洋医学により改善しない全てに及びます(運動器疾患から神経系、消化器系、循環器系、免疫系、代謝系、リンパ系、呼吸器系、五感の症状、ストレスなどのメンタルヘルス、不定愁訴など)。
鍼灸は様々な症状の改善に適しており、人のもつ自然治癒力を引き出しながら病気を治し、体質に変化を与えることに優れています。
効果は体質や病勢によりさまざまですが、鍼灸を受けることで今よりも快適な生活を送ることできるでしょう。
参考書籍 間中喜雄「針灸の理論と考え方」|創元医学新書 1971
患者さんと鍼灸の適応症状について話をしていると、「鍼灸は高齢者が受けるものだと思っていました」という声を聞きます。
つまり腰痛や膝痛に対するものだと思うそうなのです。
しかし実際には沢山の症状に対して適応します。
なぜ筋肉や関節の症状ばかりが注目されるかというと、単純に理学療法の一部として認知されているからだと思います。
なぜ筋肉や関節の症状ばかりが注目されるかというと、単純に理学療法の一部として認知されているからだと思います。
つまり、鍼という物質を「硬い筋肉に対して鍼を刺して弛めているのだろう」という単純明快なものがあるのでしょう。
しかし、実際には1~4のようなことが起きています。
1.体性-内臓(自律)反射:内蔵、自律神経のコントロールを行い調整する作用.。
2.軸索反射:鍼灸を施術した部位の血管を広げたり、血液の流れを良くしたり、痛みの物質を流すなどの作用。
3.鍼麻酔(鍼鎮痛):鍼灸の刺激は脳に伝わり、やがて鎮痛効果のある物質を分泌、また放出し、痛みを和らげる作用。
4.ゲートコントロール:鍼灸を施術することで、痛みを脳に伝える前段階で痛みの抑制をかけ、痛みを和らげる作用。
女性の身体の不調、内臓の症状に対して鍼灸が有効である理由もここで紹介されていますが、筋肉に鍼灸の刺激を与えることで【体性-内臓反射】という作用を使いアプローチします。
これは難しい話ではありません。
筋肉以外の症状でお困りの方はぜひ鍼灸をお選びください。