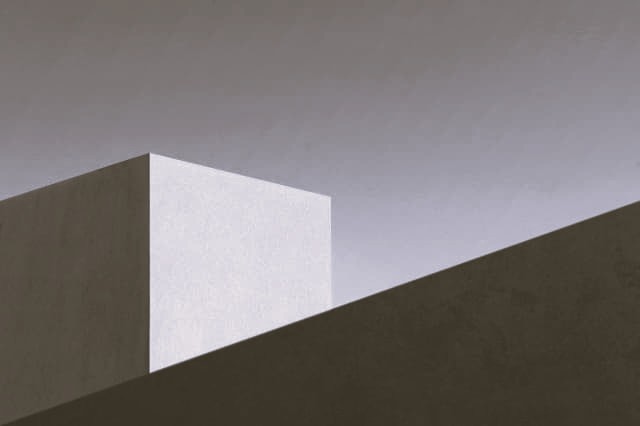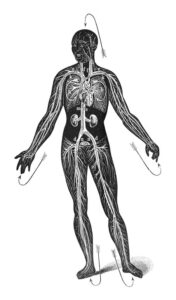患者さんに「鍼と灸の違いは何ですか?」という質問を受けることがあります。
鍼は経絡の滞りを整え、痛みや凝りをやわらげる働きがあり、神経系に作用して局所の血流改善に効果的です。
灸は温熱で冷えを改善するだけではなく、免疫力を高め、回復力を高めます。
以下の内容(鍼灸の科学 理論篇)は、東京教育大、筑波大教授を経て名誉教授であった医学博士の芹沢勝助先生が鍼灸の定義としてまとめたものです。
鍼施術は一定の方式により「鍼」を用いて体表より接触、穿刺し、機械的刺激を生体に及ぼし一定の生体反応を起こして、生体の示す変調を矯正し、また疾病治癒に寄与する方法であって、保健、疾病予防、治療に広く応用する施術である(定義)。
灸施術は一定の方式により「もぐさ」またはこれに類する物質を用いて、燃焼し体表より温熱的刺激を生体に及ぼし、一定の生体反応を起こして、生体の示す変調を矯正し、また疾病治癒に寄与する方法であって、保健、疾病予防、治療に広く応用する施術である(定義)。 参考書籍 芹沢勝助「鍼灸の科学 理論篇」|医歯薬出版株式会社 1959
このように鍼灸はただ刺しているだけでも、温めているだけでもなく、意図的に機械的刺激を生体に与えて生体反応を起こし、変調を矯正することが分かります。
もっと深堀すれば、鍼が金属である理由、灸が植物のなかでヨモギを使う理由もありますし、陰陽の考えもあります。
また鍼はどうやっても補えず、灸はどうやっても奪えない。
それは性質の話で、機能的にもそうなっていますから、「鍼は散らす」「灸は収める」というように考えていただけたら良いでしょう。