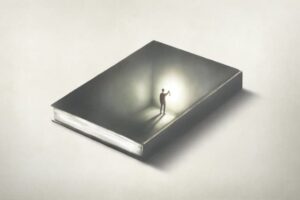先日、元スポーツ選手の方が来院しました。
年齢は40代、主訴は右の腰痛であり、起床時に筋肉が痛くて起きられないといいます。
全体を診ると右背部の筋肉が大きく発達しており、過去の右膝op、右足関節遊離体op、腹部内視鏡op歴がありました。
本人はこれらのことが影響しているとは考えていませんが、身体を傷つけ開くことによる負担は想像以上に大きいものであることがよく分かります。
鍼も同様のことが言えるのかというと、鍼によって傷つけられた組織は内部の圧力と外部の圧力により塞がるため、創部のようにはなりません。
生命体はあらゆる方法をとり生き延びる方法を選択しますが、それによる代償として今回は皮膚の釣れ、関連する筋肉への負担、体幹を安定させるために起こる微妙な変化が蓄積されたことが要因としてあげられます。
彼女はこれまで、大学、実業団でバスケットボールに汗を流してきたので筋肉に対する造詣が深く、どこの筋肉に鍼を刺せば効果があるのかは理解していました。しかし、それでも再発してしまう理由は分からなかったそうです。
今回、過去の既往歴についての話をした際に彼女は上の空で聞いていたのですが、全ての内容に辻褄があっていることで、ようやく理解を示してくれました。
過去の身体の傷は無くなりはしませんし、塞がったからといって0にはならず、その傷を治すために大きなエネルギー消耗は起きています。
また、何もないように感じていても、その情報処理をしているのは脳であって、無意識に身体にはその歪は生じます。
今回、腰痛を訴えてはいましたが、その背景にあるものが単に筋肉の問題ではないことに気づき、予診票に記載していない既往歴を確認したことでみえできたこともあるのですが、それは必ず腹に現れます。
腹部の均一化をはかる、というものはとても重要であり、局所をコントロールすれは良くなるという単純なものではありません。
鍼灸師としては、ただ局所に鍼を刺すという芸ではなく、文化を残す藝としての鍼をおこなっていきたいものです。
そのことを学ぶ機会になりました。